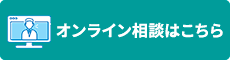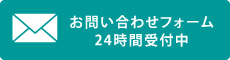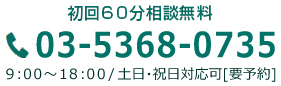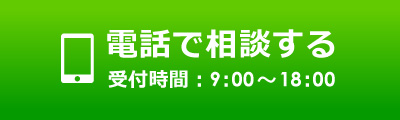以下のとおり、相続が発生した時期によって適用される法律が異なるため、法定相続分の割合が現在と異なるケースがあります。
〈昭和 22年 5月 3日から昭和 55年 12月 31日まで〉
・相続人が配偶者と直系卑属の場合
→ 配偶者 1/3、子 2/3(子が複数いる場合は 2/3 を頭数で除した割合)
・相続人が配偶者と直系尊属の場合
→ 配偶者 1/2、親 1/2(父母がいずれも存命中の場合は 1/4 ずつ)
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
→ 配偶者 2/3、兄弟姉妹 1/3(兄弟姉妹が複数いる場合は頭数で除した割合)
(※)昭和 56年 1月 1日以降に発生した相続から、兄弟姉妹の再代襲相続が認められないことになりました(昭和 23年 1月 1日から昭和 55年 12月 31日までは、認められていました)。
〈昭和 22年 5月 2日以前〉
戸主が亡くなった場合、原則として、法定家督相続人のみが相続人となります。
家督相続人になるのは、亡くなった方の戸籍に同籍していた子の年長者であり、通常、長男が家督相続人になりました。
なお、戸主以外の人が亡くなった場合は「遺産相続」という取扱いのもと相続人が決定するのですが、専門的な知識が必要になるケースが多いため、一度ご相談されることをお勧め致します。