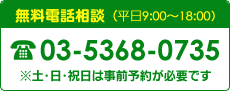遺留分減殺請求の行使方法と訴訟への流れ・費用について
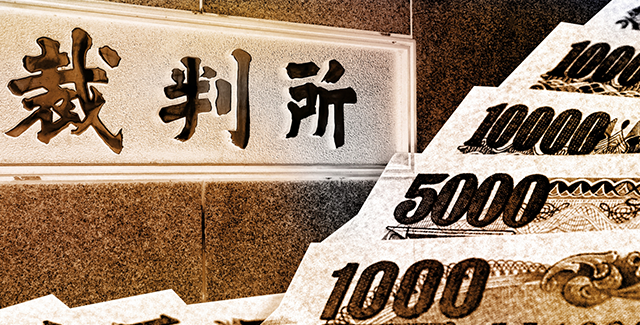
遺留分の制度は、被相続人(亡くなられた方)が持っていた財産(相続財産)について、その一定割合の取得を、一定の法定相続人に保障する制度です。
この「一定割合」を確保することができる地位を「遺留分権」といい、遺留分を持っている法定相続人のことを「遺留分権利者」といいます。
(ご自身に遺留分があるかどうか及びその算定方法については、こちらの記事をご参照下さい。)
今回のテーマは、遺留分減殺請求の行使方法と、その後の手続の流れ、訴訟に至った場合の費用等についてです。
ちょっと難しい部分もありますが「ポイント(☑)欄」をご覧になれば、要点はご理解いただけると思います。
1 遺留分減殺請求権の行使方法について
遺留分減殺請求権は、自己の遺留分を侵害された遺留分権利者が、自己の遺留分を保全するのに必要な限度で、贈与や遺贈(遺言で財産を贈与すること)といった行為の減殺を請求することができる、というものです(民法1031条)。
この遺留分減殺請求権は、必ず訴訟を提起して行使しなければならないというわけではなく、相手方に対する意思表示、つまり、「遺留分を侵害しているので、侵害している行為(贈与や遺贈)について減殺します」という意思を相手方に表示すれば足りる、とされています(最高裁判所昭和41年7月14日判決)。
一般的には、あとから「いつ・どのような意思表示をしたのか」という点を証明できるように、内容証明郵便などを使って、相手方(遺留分を侵害している人)に意思表示を行うことになります。
また、遺留分減殺請求の意思表示は、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。」とされていますので、行使に期限があることにも注意しましょう。(民法1042条)
次に、遺留分減殺請求権は、行使する対象に順序があります。
例えば、遺留分を侵害するような遺贈と生前の贈与があったと仮定しましょう。
この場合、遺贈を減殺した後でなければ、生前の贈与を減殺することができません。(民法1033条)
つまり、遺留分減殺請求権行使の順序としては、贈与より遺贈が先になります。
ちなみに、複数の贈与がある場合は、後の(現在に近い)贈与から前の(昔の)贈与の順に遺留分減殺請求権を行使できます。
また、複数の遺贈があった場合ですが、この場合は、遺贈の目的の価額の割合に応じて(※)減殺することになります。(民法1034条)
ただし、亡くなられた方が遺言で別段の意思を表示しているときは、その意思に従うことになります。
上記(※)の「遺贈の目的の価額の割合に応じて」という意味を、具体的なケースでご説明します。
遺留分が「2000万円」侵害されているという場合において、A不動産(2000万円)とB(6000万円)の不動産が遺贈されているケースでは、以下の割合で減殺することになります。(ざっくり言えば、取得した財産の価額割合という意味です。)
A不動産
2000万円×2000万円÷(2000万円+6000万円)=500万円
B不動産
2000万円×6000万円÷(2000万円+6000万円)=1500万円
なお、上記のケースは、第3者(相続人以外の方)に対する遺贈の場合ですが、共同相続人の一部が遺贈を受けている場合は、遺贈された財産の価額のうち、当該相続人の遺留分をこえる部分のみが減殺の対象となります(最高裁判所平成10年2月26日判決)
つまり、その相続人自身の有する遺留分を超えている部分のみが、遺留分減殺請求の対象になるということです。
☑遺留分減殺請求権は、手紙(内容証明郵便)でも行使できる。
☑遺留分減殺請求権の行使には、相続の開始等から1年の時効があることに注意する。
☑遺留分減殺請求権の行使には、行使の順序や決まりがある。
2 遺留分減殺請求権を行使した後の手続の流れ
例えば、ある不動産の遺贈がされたケースで、その遺贈が遺留分を侵害するとして「遺留分減殺請求権」を行使した場合を取り上げてみましょう。
このケースで、遺留分の侵害額が遺贈対象となった財産の価値を超える場合(遺留分侵害額>遺贈された財産)は、その遺贈対象となった財産全体が「遺留分減殺請求を行った人」のもとに取り戻される、という効果が生じます。
逆に、遺贈の一部分が遺留分減殺の対象となった場合、つまり、遺留分の侵害額が遺贈の対象となった財産の価値に及ばないとき(遺留分侵害額<遺贈された財産)は、どうでしょうか?
この場合は、遺贈対象となった財産の一部だけが取り戻されることになりますから、「遺贈を受けた方」と「遺留分減殺請求を行った方」との間で、不動産が共有状態になります。
ここで言う共有状態は「相続財産を相続人全員が共有している」という状況ではなく、あくまで、「遺贈を受けた方」と「遺留分減殺請求を行った方」との、2人の間での共有関係ということになります。(民法1041条の「価額による弁償」をした場合を除く)
そして、この場合は、民法の「共有」に関する規定が適用されます。
したがって、この共有関係を解消するためには、
①共有物の分割について、共有者間で協議を行う
②共有者間での協議が整わないときは、裁判所に対して共有物の分割を請求する(民法258条)。
ことになります。
☑遺留分減殺請求権の行使によって共有関係になることがある
☑共有関係を解消するには、①当事者間での協議と②裁判所での共有物分割訴訟の2通りがある
3 専門家に共有関係の解消を依頼する場合の費用感
遺留分減殺請求権の行使により共有関係にならない場合(遺留分侵害額>遺贈された財産)については、対象財産が「遺留分減殺請求を行った方」の単独所有となりますので、遺贈を受けた方に対して、当該財産の引渡し請求等を行うことになります。
この場合、対象となる財産の受け渡すだけで済んでしまうので、単純に「不動産の名義変更」などをして完了させる場合も多いです。
しかし、遺留分減殺請求を行って共有関係になった場合(遺留分侵害額<遺贈された財産)、共有関係の解消はなかなか一筋縄ではいきません。
解消方法として、「遺贈を受けた方」と「遺留分減殺請求を行った方」のどちらかの単独所有にする方法(共有持分を失う方に対して、その割合に応じた金銭を支払うことに)や、共有関係にある不動産を第三者に売却して、その代金を持分の割合に応じて分けるという方法もあります。
しかし、どちらの方法も不動産の売却や不動産価格の査定(鑑定)といった手続きが必要になりますので、「不動産の売却金額に合意できない」、「相手方の査定額が低すぎる」等として争いになることが多いです。
ですから、共有関係の解消が必要になってしまった場合は、専門家に相談をして対応することをおススメします。
なお、この共有関係の解消について、弁護士に「相手方との交渉を依頼する場合」や「共有物分割訴訟を依頼する場合」は、費用の目安としては、侵害された遺留分の算定額の5~8%相当が着手金として必要になることが多いです。(あくまで一般的な相場感です)。
ご依頼をされる際は、料金体系とサービス内容をしっかり確認することも大切です。
☑共有関係の解消については紛争になりやすく、専門家に任せるのが安心。
☑弁護士費用は自由化されているが、概ねの費用感・相場はある
当窓口では、様々な立場の方から遺留分に関するご相談を受けているため、遺留分の算定はもちろん、相談者様の立場に立った対応やご提案が可能です。
遺留分を考慮した遺言の作成や、遺留分減殺請求を受けた場合の対応などについても対応しておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
また、「遺留分減殺請求の訴訟を起こされてしまった・・」、「遺留分の支払いに応じてもらえないので裁判をしたい!」という方については、遺留分に関する訴訟に精通したパートナー弁護士による訴訟対応のサービスもご用意しております。
詳細はお問い合わせください。
私たちのサービスが、お役にたちますように。
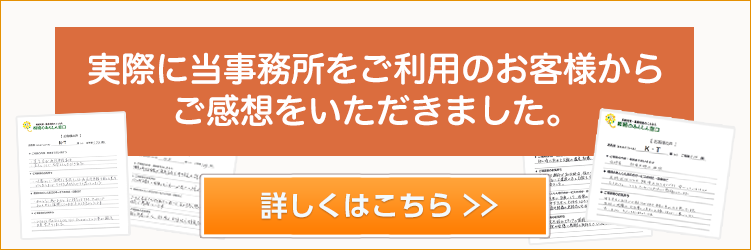
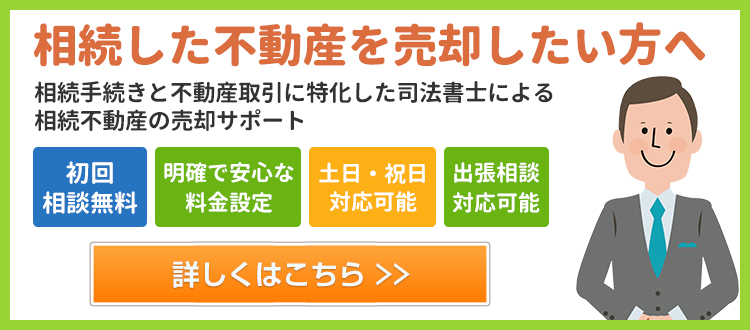
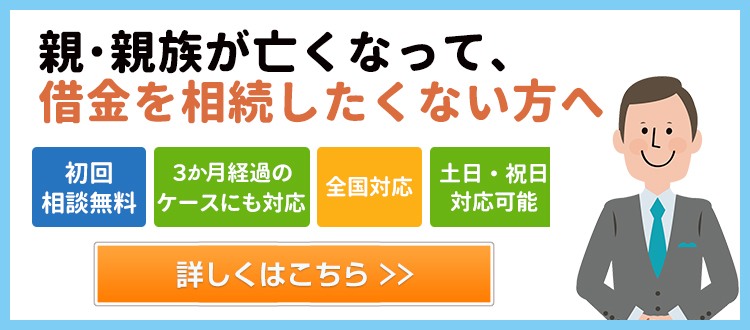
関連記事合わせてお読みください

不動産の共有持分の相続に関する「トラブル事例」とその「解決方法」とは?
複数の相続人で不動産を相続した場合に、非常に多く発生する問題が「共有持分」にまつわるものです。 なぜなら、複数の相続人の共有となった土地や建物は「共有者全員」の意思が一致しない限り、売却などの処……


相続した不動産を売却して現金化した場合、どんな税金がかかるの?
相続した不動産を売却して、その売却代金を相続人で分けるケースも少なくありませんが、その際の税金の取扱いはどうなるのでしょうか? 今回は、相続した不動産を売却して売却代金を相続人で分ける、いわゆる……


相続した借地権の売却について
当窓口では、相続した不動産に関する様々なご相談に対応しておりますが、その中でも「借地権を相続したのですが、売却するにはどうしたら良いのでしょうか?」というご相談は少なくありません。 相続により引……