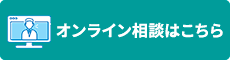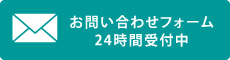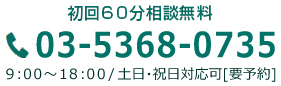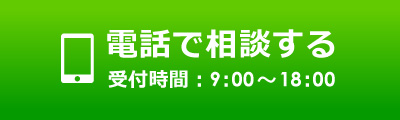相続実務Q&Aの記事一覧
- 相続登記の申請義務はありますか?また、申請期限はありますか?
- 相続登記を申請しなかった場合、何かリスクはありますか?
- 何代にも渡り相続登記をしていなかった不動産の相続登記をする場合、どのような手続きをすることになるのでしょうか?
- 遺言による相続登記や遺贈の登記は、どのように行うのでしょうか?
- 相続登記をする不動産の登記記録上に、完済した住宅ローンの抵当権が残っている場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
- 相続した土地上には建物が現存していないにもかかわらず、建物の登記が残っているようです。どのように対応すればよいでしょうか?
- 相続登記の登録免許税は、どのように計算するのでしょうか?
- 相続登記をするには、どのような書類が必要でしょうか?
- 相続登記には、戸籍等の原本が必要ですか?コピーでもよいのでしょうか?
- 相続登記に利用する「遺産分割協議書」に添付する印鑑証明書に有効期限はありますか?
- 不動産の相続登記が義務化される?過料はいくら?手続きにかかる費用は?
- 遺言には、どのような種類がありますか?
- 遺言書保管制度を利用する場合、どのような流れになりますか?
- 遺言書保管制度の利用にあたって、注意することはありますか?
- 認知症の場合、遺言を作成することはできないのでしょうか?
- 成年被後見人は、遺言の作成はできないのでしょうか?
- 遺言で「二次相続が起きた場合の財産の承継先」を指定できますか?
- 自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度とは、どのような制度ですか?
- 特定の相続人の遺留分を侵害する遺言書は、法的に有効ですか。
- 遺言を勝手に開封すると罰金が発生するのでしょうか?
- 遺言で遺言執行者を定めておいた方がよいのでしょうか?
- 遺言執行者には誰がなれるのでしょうか?
- 遺言執行者には、どのような権限がありますか?
- 遺言書で遺言執行者に指定されている場合、相続開始後に何をすればよいですか?
- 自筆証書遺言があるか不明な場合、どのように調べたらよいでしょうか?
- 遺言書が見つかった場合は、どのように対応したらよいのでしょうか?
- 自筆証書遺言の検認手続きとは、どのような手続きですか?
- 公正証書遺言の調査方法
- 遺産分割協議書には、相続人全員の「署名」と「実印での押印」が必須ですか?
- 遺言の内容と異なる遺産分割協議は可能ですか?
- すでに遺産分割協議が成立している場合、遺留分の請求や遺産分割協議のやり直しはできますか?
- 遺産分割協議書に預貯金を記載する場合、具体的な残高を書いた方がよいのでしょうか?
- 遺産分割協議書に「生命保険金」や「死亡退職金」などの記載は必要でしょうか?
- 遺産分割協議において「被相続人の債務を特定の相続人がすべて引き受けること」を合意した場合、その合意は債権者にも対抗できるのでしょうか?
- 同一内容の遺産分割協議書を数通作成し、各相続人が別々に署名と押印している場合、遺産分割協議書として有効でしょうか?
- 遺産分割協議書の不動産の地目や地積については、固定資産評価証明書と登記事項証明書のどちらを書いた方がよいでしょうか?
- 遺産分割協議に非協力的な相続人がいる場合、どのように対応すれば良いでしょうか?
- 換価分割とは、どのような遺産分割の方法ですか?
- 代償分割とは、どのような遺産分割の方法ですか?
- 遺産分割協議の成立前に相続財産である不動産から生じた賃料については、当該不動産を取得した相続人が受け取れるのでしょうか?
- 相続登記に使用する遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印をして、印鑑証明書を添付する必要がありますか?
- 遺産の一部について、遺産分割協議をすることもできるのでしょうか?
- 遺産分割協議が成立するまで、預貯金の払戻しを受けることはできないのでしょうか?
- 遺産分割協議前に遺産が処分された場合はどうなりますか?
- 一部の相続人が海外に居住していて印鑑証明書の発行ができない場合、どのように対応したらよいでしょうか?
- 遺産分割協議の当事者に未成年者の子がいる場合、どのように対応すればよいでしょうか?
- 相続人の中に行方不明の者がいる場合は、どのように対応したらよいのでしょうか?
- 預貯金の払戻し制度を利用する場合の注意点はありますか?
- 遺産分割前の預貯金の払戻し制度とは何ですか?
- 預貯金債権の仮分割の仮処分制度とはどのような制度でしょうか?
- 遺産分割協議がまとまらない場合や、一部の相続人が協力してくれない場合は、どうしたらよいのでしょうか?
- 遺産分割調停は、具体的にどのような流れで進むのでしょうか?
- 遺留分侵害額請求権は、どのように行使したらよいのでしょうか?
- 相続人への生前贈与は、何年前のものまで遺留分の算定に組み込まれますか?
- 底地を相続した場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
- 信託契約の内容は、途中で変更できますか?
- 委託者の死亡によって家族信託が終了した場合、信託財産はどうなるでしょうか?
- 相続した借地権付き建物を売却したい場合、どうすればよいのでしょうか?
- 死因贈与契約は、どのようなときに効果的ですか?
- 代理による信託契約
- 信託契約は、公正証書で作成する必要がありますか?
- 認知症対策として家族信託を利用するには、どれくらいの期間がかかるのでしょうか?
- 自益信託・他益信託とは何ですか?
- 受託者は、信託の報酬を受け取ることが可能でしょうか?
- 遺言代用信託とは何ですか?
- 株式会社の定款について、相続対策になるような規定はありますか?
- 株主に相続が発生した場合、どのような処理をすることになりますか?
- 合同会社の定款について、相続対策になるような規定はありますか?
- 会社の役員が亡くなった場合、登記を変更する必要はありますか?
- 親族が後見人になることを阻止したい場合、どうしたらよいのでしょうか?
- 親族が後見人等になる場合、注意することはありますか?
- 株主に成年後見人がついた場合、株式の取扱いはどうなりますか?
- 法定後見と任意後見は、何が違うのでしょうか?
- 財産管理委任契約と任意後見契約の違いは何でしょうか?
- 財産管理委任契約とは、どのような契約でしょうか?
- 「見守り契約」とは、どのような契約でしょうか?
- 借地権を相続した場合、地主に承諾料を払う必要がありますか?
- 成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)とは、どのような制度ですか?
- 相続放棄をしたにもかかわらず、相続財産について責任や義務が生じることはありますか?
- 相続放棄の申述が受理されたあと、注意をしなければいけないことはありますか?
- 被相続人の預貯金を引き出して葬儀費用を支払ってしまった場合、相続放棄はできないのでしょうか?
- 葬儀費用を相続財産から支払ってしまった場合、相続放棄はできないのでしょうか?
- 不動産について死因贈与契約をした場合、贈与者の生前の処分を制限することはできますか?
- 法定後見を利用するにあたって、親族が後見人等になりたい場合、必ず選任してもらう方法はありますか?
- 借地権を相続した場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
- 法定後見を利用した場合、途中でやめることはできますか?
- 相続人に対する売渡し請求に基づく売渡価格は、どのように決まりますか?
- 被相続人の「契約者(債権者・債務者)の地位」は、相続人に相続されますか?
- 相続手続きを何もしていないケースにおいて、被相続人宛に借金の返済の督促などがきた場合、どのような対応をするべきですか?
- 被相続人が連帯保証人になっていた場合、その地位は相続人に承継されますか?
- 預貯金の財産調査はどのように進めたらよいでしょうか?
- 貸金庫はどのように調査すればよいでしょうか?
- 借入債務(借金)などの調査は、どのようにしたらよいでしょうか?
- 株式(株券電子化に未対応の株式・単元未満株)の調査は、どのようにしたらよいでしょうか?
- 不動産の調査は、どのように進めればよいでしょうか?
- 相続財産管理人が選任された後は、どのように手続きが進みますか?
- 遺産分割協議書中、「土地」・「建物」・「敷地権付区分建物(マンションなど)」・「未登記建物」はどのように記載すれば良いでしょうか?
- 何世代も前の相続から手続きをしていない場合、注意すべきことは ありますか?
- 日本における同性愛者間の婚姻・相続関係は、どのような取扱いになっていますか?
- 非嫡出子とはどのような存在ですか? また、相続分はどのような取扱いになるのでしょうか?
- 法定相続情報証明制度を利用する場合、注意点はありますか?
- 配偶者短期居住権とはどのような権利でしょうか?
- 配偶者短期居住権は、どのようなときに消滅しますか?
- 配偶者居住権は、どのようなときに消滅しますか?また、消滅後はどのような手続をすることになりますか?
- 配偶者居住権を譲渡(売買・贈与など)することはできますか?
- 生命保険金は、特別受益に該当するのでしょうか?
- 特別受益とは何ですか?
- 遺留分とは何ですか?また、遺留分侵害額請求権とはどのような権利ですか?
- 葬儀費用は、民法上の相続債務に該当するのでしょうか?
- 死因贈与契約と遺言の違いは何でしょうか?
- 葬儀費用の負担については、遺産分割協議書に記載するべきでしょうか?
- 特定の相続人が葬儀費用を負担した場合、他の相続人に一部の負担を求めることはできますか?
- 相談者が相続放棄を希望しているが、「被相続人の死亡から3か月を超えている場合」は、どのように対応すればよいでしょうか?
- 相続放棄をした場合、お墓を継ぐことはできないのでしょうか?
- 相続放棄は、相続放棄の対象者が生存中でもできるのでしょうか?
- 相続した不動産を売却する場合に注意をすることはありますか?
- 相続した不動産を売却して現金化したい場合、どのように手続きを進めればよいでしょうか?
- 相続登記前に合筆の登記をすることはできますか?
- 合筆登記には、どれくらいの期間がかかりますか?
- 相続登記の前に分筆登記をして、分筆後の土地を相続人が単独で取得する遺産分割協議を行いたい場合、どのような内容にすればよいでしょうか?
- 分筆登記には、どれくらいの期間がかかりますか?
- 特別受益の持ち戻しの免除とは何ですか?
- 相続人の中に成年被後見人がいる場合は、どのように対応すればよいでしょうか?
- 「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」で引き出せる金額はいくらでしょうか?
- 遺留分は、どのように算定するのでしょうか?
- 遺留分は、生前に放棄することはできるのでしょうか?
- 法定相続人 相続が発生した場合、だれが相続人になりますか?
- 死因贈与契約書は公正証書で作成した方がよいでしょうか?
- 相続した底地を売却したい場合、どうすればよいのでしょうか?
- 家族信託を活用したモデルケースを教えてください。
- 家族信託と後見制度(法定後見・任意後見)の違いは何ですか?
- 家族信託とは、どのようなものでしょうか?
- 遺言と家族信託はどちらが優先されるのでしょうか?
- 株式の調査は、どのようにしたらよいでしょうか?
- 相続人がいない場合、被相続人の債権者などは、どのように対応することになるのでしょうか?
- 合筆登記とはどのような手続きですが? また、手続きにはどのような書類が必要ですか?
- 分筆登記とはどのような手続きですか? 手続きにはどのような書類が必要ですか?
- 「死亡退職金」・「小規模企業共済の共済金」・「生命保険金」は相続財産ですか?
- 配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いは何でしょうか?
- 分筆登記は、相続登記の前に行うことはできますか?
- 配偶者居住権とは、どのような権利でしょうか?
- 配偶者居住権は、登記できるのでしょうか?
- 相続放棄は、被相続人の“ 死亡日から3か月以内” にしないと認められないのでしょうか?
- 法定相続情報一覧図の写しが足りなくなった場合、追加で再交付をしてもらえるのでしょうか?
- 相続人の法定相続分は、どのような割合になりますか?
- 法定相続情報証明制度は、どのように利用すればよいのでしょうか?
- 法定相続情報証明制度とはどのような制度でしょうか?
- 相続放棄をした場合、税金の納付義務はどうなるでしょうか?
- 相続放棄の申述手続きを依頼した場合、どれくらいの期間がかかりますか?
- 相続放棄の申述手続きには、どのような書類が必要ですか?
- 他の相続人の相続放棄の状況を確認する方法はありますか?
- 遺産分割協議を避けるために未成年者の子が相続放棄をする方法があると聞きました。そのようなことはできるのでしょうか?
- 「相続放棄」と「遺産放棄」は、同じ意味でしょうか?